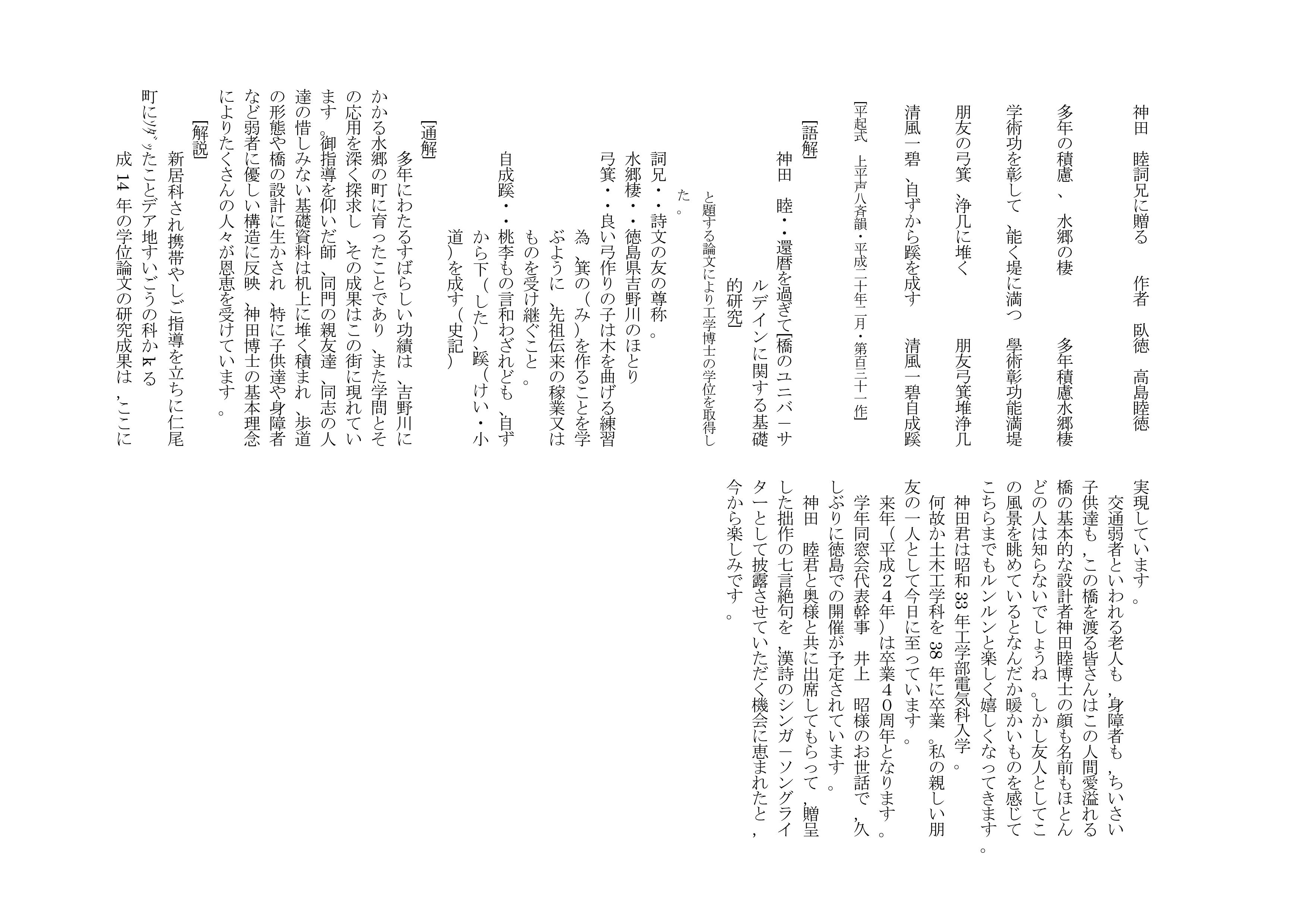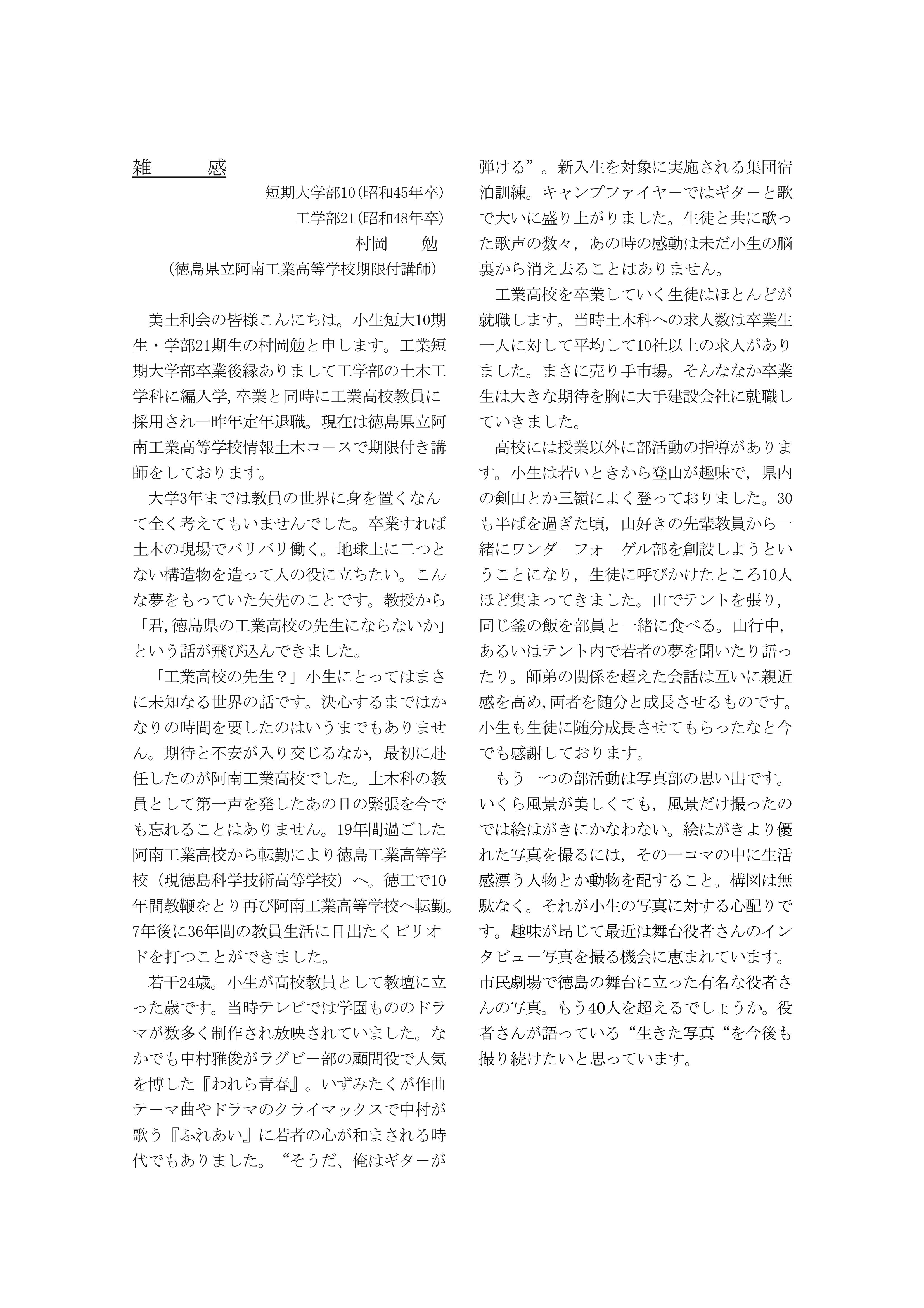物作りとしての 「陶芸工学」
工学部12(昭和39年卒)
佐 岡 暖 也
昭和39年卒の同窓生の諸兄!ご無沙汰です。
私事ですが、今年(平成23年)3月、兵庫県生きがい創造協会いなみ野学園(高齢者大学)陶芸学科(4年制)を卒業しました。知事などの列席のもと卒業記念作陶展(花器など4作品以上出展)も無事クリアし、作陶の免許皆伝(?)を授与されました。4年間の積もり積もった不燃物ガラクタ陶器は処分しても足・腰痛が残りましたが、それにも懲りず、引き続き4月から県の「陶芸の村」に通いはじめております。現役時代の物つくりとは違う粘土での「物つくり」に生きがいを見つけたと申しますか、これしかないと、老いの手習いに苦戦と至福の時をもっております。
長大橋建設盛隆期の現役時代に、「橋梁工学」を専攻、鉄構会社に入社し、本四架橋では大鳴門橋、南北備讃瀬戸大橋、来島大橋の設計関係に関わる共に、明石海峡大橋では、現場代理人・所長として設計・製作・工事に携わりました。また、阪神大震災では、震災直後無残に崩れた橋梁群の現場に立っていとおしく涙があふれ、関係者の連日・連夜の復旧工事に汗を流した人間の底力を思い知るなど、橋・「物つくり」一筋の会社人生でありました。今、東日本大震災では、阪神大震災とはその規模、時間は比較にならないと思いますが、復旧・復興に向けて人間の底力を確信しております。こんな技術畑一直線の男が、4年前に何をどう血迷ったのか「陶芸」をやることになりました。「芸(芸術)」には縁遠く、感性もセンスもない者にとって、まったく未知の世界に入り苦戦と諦観の境地に直面している次第です。
土木工学では、粘土は厄介者でしたが、陶芸では粘土(陶土)によって作品の表情をいろいろと表現できます。一般的な作陶の手順は、粘土を成形→乾燥→素焼(約800度)→釉薬(うわぐすり)掛け→本焼(約1250度)となります。この工程の中に絵付けなど種々の技法があります。粘土は、白い粘土、砂・小石混じりの粘土、鉄分を含んだ赤い粘土など産地・成分とブレンドにより多くの種類があります。釉薬は、灰系(基礎釉)、鉄系、銅系など市販のものと、また、個人で調合したものなど無限になります。さらに、本焼窯での炎の加減(酸化・還元焼成)で、思わぬ表情と発色が出(景色)て、その出来栄えは神頼みに近いものがあり、奥が深いと言われます。これこそ、教えられるものではなく、経験し修得するしかなさそうです。橋屋の「物つくり」とは全然異にします。そのためか、粘土成形時でも凸凹や、構造バランスの悪いものは気にかかり、到底、オブジェなどは自分には性に合いません。こんな状況にて、芸術作品など程遠く、「ボケ」防止のための粘土細工による工学的作陶と割り切っております。身近な湯呑み、茶碗などを作っても、重たいと言って誰ももらってくれず(陶芸では所望される以外、人様に差し上げると言っては駄目だそうです)、夫婦の日常生活に手つくり食器として使う楽しみ程度です。時々、妻のきつい評価を聞き流しながら。そう、我が家のペット(トイプードル)は餌食器として黙って使ってくれています。後は不燃物ガラクタとしてゴミ処分されます。ただ、陶芸みたいなものをやっていたらしいいという証しとして、孫達に陶印(サイン)を刻したオンリーワンの湯呑みか茶碗を残すことを夢見ています。
NHK大河ドラマ“江”のなかで、千利休が使った黒楽茶碗は、利休が変化・誇張・装飾などを極限におさえて長次郎に焼かせた抹茶茶碗の設定と思います。楽茶碗は、楽土を手づくね成形により、口縁は僅かに波打ち、丸みのある胴にぬくもりを感じます。時々、自分で焼いた黒楽茶碗(赤楽もあります)もどきで、夫婦で簡単な抹茶を立て、3時を味わうのもなかなか良いものです。陶芸に出会った賜物です。
(黒楽茶碗もどき)
昭和39年卒の同窓諸兄も、今年で全員が古希を通過すること、めでたい限りです。統計によれば、70歳では平均余命が約15年だそうです。まだ15年、もう15年です。平均余命ではなく健康余命(寿命)とし、子のため妻のため、ピンピン・コロリを心掛けようではありませんか!
昭和42年4月入学及び昭和46年3月卒業の同窓会
昭和42年4月入学及び昭和46年3月卒業の同窓会とボロボロの三年生
工学部19(昭和46年卒) 岡田 泰一
平成23年6月11日(土)に上記のうち16名が出席して、岡山県鷲羽山の麓の下電ホテルで恒例の同窓会を開催した。宴に先立ち10名は、ゴルフ で一足先に一汗かき、親睦を深めた。42年入学組はその年から定員が30名から40名に大幅増となり、右肩上がりの始まり時期でもあった。今回幹事のほう で初めて名簿を作成。その名簿によると該当者40名のうち、物故者が3名。その時期は、平成23年3月に志田原務、平成21年11月に岡部健士、榎本治 は、卒業して間もなくであった。近年の両名は同窓会の常連であっただけに、無常を感じざるを得ない。卒業後、各自それぞれの道を歩み、現在は悠悠自適の 者、再就職して現役以上に頑張っている者等々・・・・。この同窓会は近年毎年実施しており、今回、遠方からでは、南は沖縄から、東は神奈川県横須賀市、北 は石川県白山市からの参加であった。写真は、前回の平成22年7月3日(土)、香川県のヴィラ讃岐での時である。
さて、自分はボロボロの三年生。県を定年退職し、3年目です。一年が年齢と共に早く過ぎ去るように感じられます。自分だけでしょうか。充実した日々を過ごしたお陰でしょうか。
< 光陰矢のごとし >
近年、残念ながら同輩の急逝が続く。改めて、健康な身体に感謝するするとともにある出来事を思い出し、糧にしたい。
< 一寸先は闇 >
時は、平成18年8月に異変が生じる。恒例の昼のジョギング中にスタートから5~10分で右肩付近に違和感が生じ、初めて立ち止まり、中止。翌日 も同様な症状が生じ、何か悪い予感が。宇和島市内の循環器科を受診。問診のあと、心電図を。担当医は狭心症であり、心筋梗塞を防ぐため早期の処置が必要な ため直ちに宇和島市民病院に連絡するから行くようにと進言。当時、松山からの通勤のため、松山地区の病院の紹介を依頼すると、県立中央にTelし紹介状を いただいた。 県中央病院に検査入院しカテーテルと造影剤にて冠動脈の閉塞状況等をわずかな時間(30分弱)で把握。その結果をパソコンの画面と処置の方 法等の説明を妻と聞き、ステント挿入を選択決定し、善は急げと翌日ステント治療を行った(入院:平成18年8月22日、退院:8月27日)。
< 健康は富にも勝る>
以後、血液を固まりにくくする薬を朝晩の2回服用している。治療から間もなく5年。現在もフルマラソンはドクターストップ中だが、脈拍数が1分間 に120程度(ATレベル以下)の運動は勧められている。また、発汗に伴う血液のドロドロを防ぐため水分補給が重要。現在、ゆっくりジョグを復活し続けて いる。
< 蒔かぬ種は生えぬ >
ルーの法則を実感しているこの頃である。
自分は35歳の時に5分走からはじめて、愛媛マラソンに22回連続完走、中島トライアスロン10回連続完走や県庁遊走会の創設に関係し駅伝等に参 加し現在も遊走会は盛会に続いております。走り始めたころの約30年前には、ジョギングブームの始まりの時期であった。ジョギングの神様またはジョギング の教祖といわれたジェイムズ・フィックス(1931から1984年。52歳。)が著した「奇跡のランニング」(1981年)が発刊され有名であった。著者 は、30代半ばで100キロ近くまで太ってしまい減量のため毎日15Kmのランニングを続けた。その結果、30Kg以上の減量に成功。
ショッキングな出来事・・・「奇跡のランニング」の著者であるジェイムズ・フィックス氏のランニング死。ボストンマラソン6回出場。ジョガーから ランナーへの変身。健康を求めて走り始めたジョギングが1分、1秒を追求するランナーに変わった時に彼の不幸が始まりました。自らもジョギングの実践を続 けていたが日課としていたジョギング中の1984年7月20日に心臓梗塞で突然死(52歳)。
教訓 < 反面教師 > < 命あっての物種 >
また、「2本の足は2人の医者」という昔の諺がある。利活用しないのはもったいない。歩く、走るというのは人間にとっての基本。この運動は全身の 筋肉が協応して使われる。ルーの法則を簡潔にいえば、身体(筋肉)の機能は適度に使うと発達し、使わなければ萎縮(退化)し、過度に使えば障害を起すとい うものである。
< 継続は力なり > < 過ぎたるは及ばざるが如し >
冠動脈がどのくらい狭窄しているかはカテーテル検査でないと詳細にはわからない。狭心症は60歳台後半からの患者が多いそうですが。自分は、毎年 の健康診断、血液検査は良好で禁煙もしており、リスクは最小と思うのだが。医者曰く、「年をとればなりますよと」。体質、運命かとあきらめるしかないのか と思うこの頃です。でも、病気のリスクを小さくし、生活の質を高めるためには、健康が第一。そのため、運動、食事、睡眠のバランスが大事である。有言実行 あるのみ。
< 一病息災 > < 幸せは自分の中にある >
「一期一会」ではないが、「一年一会」で一年に一回は、この同窓会を一年に(最後の)一度きりだという真剣な思いで向き合おう考えております。多くの参加を祈念しております。来年の予定は香川県です。7名の香川県住人(代表者亀川)よろしく。
以上、(平成23年7月2日記)
神田 睦君 還暦の学位
工学部10(昭和37年卒)
高 嶋 睦 徳
うららかな この日,車椅子の老婦人が新町川に架かる人間愛工学から生まれた [人にやさしい橋]を快適に渡っています。平成14年の学位論文の研究成果は,ここに実現しています。
交通弱者と云われる老人も,身障者も,小さい子供達も,この橋を渡る皆さんは,この人間愛溢れる橋の基本的な設計者神田睦博士の顔も名前もほとんどの人は知らないでしょうね。しかし,友人としてこの風景を眺めているとなんだか暖かいものを感じてこちらまでもルンルンと楽しく嬉しくなってきます。
神田君は昭和33年工学部電気工学科入学。何故か土木工学科を38年に卒業。私の親しい朋友の一人として今日に至っています。来年(平成24年)は卒業40周年となります。
学年同窓会代表幹事 井上 昭様のお世話で,久しぶりに徳島での同窓会開催が予定されています。神田 睦君と奥様と共に出席してもらって,贈呈した拙作の七言絶句を,漢詩のシンガ-ソングライターとして披露させて戴く機会に恵まれたと,今から楽しみです。
(漢詩は恒例により縦書きとします)